更新日:2025年3月21日
令和4年11月20日(日曜)に『酒田の魅力紹介 in English 動画コンテスト』を開催しました。
この動画コンテストは、酒田市の生徒たちにとって地元をより深く知る励みとなり、その魅力を伝える力を磨く機会を提供することを目的としています。また、コロナ収束後の観光交流や姉妹都市間交流促進のため、「酒田の観光PR」をテーマに、動画は3分程度、海外の観光客に届くようプレゼンターは英語を使うことを募集条件に、7月~10月の期間、作品を募集しました。
7月にはオンライン学習会を開催し、酒田市ALTによる英語でのガイドの仕方・動画編集アプリの使用講座と、SIRAからは動画制作時の注意点・コンテスト表彰式当日の流れを説明しました。
11月20日(日曜)開催の作品発表上映会・表彰式では、酒田市内の中学生・高校生から応募いただいた全13作品の中から4作品が受賞作品として選ばれました。上映会・表彰式は基本的に全て英語で行われ、高校生3人が司会者となりました。
会場への観覧参加者はコンテスト応募者を含めた62名でした。審査員長にSIRAアドバイザーの矢野慶汰氏、審査員にはSIRAアドバイザーでニュージーランド出身のティム・バンティング氏、アメリカ出身のALTキャサリン・ヘイズ氏、フィリピン出身のALTフェイリン・サンディエゴ氏を迎え、「最優秀賞(1作品)」と「優秀賞(2作品)」を選考していただきました。
また、姉妹都市アメリカ合衆国オハイオ州デラウェア市との交流促進のため、昨年度に引き続き、最優秀賞に並ぶ「デラウェア賞(1作品)」をキャロリン・ケイ・リグル市長より選考いただき、さらに応募作品に対するビデオメッセージも送っていただきました。そして、今回初めて中学生のチームがコンテストに参加してくれたことから、矢野審査員長より健闘をたたえて「チャレンジ賞」が贈られました。
表彰された4受賞者には、トロフィー、賞状および賞品としてQUOカードが贈られました。
受賞作品は、酒田市公式YouTubeチャンネルにて1年間(公開期間:2022年12月1日~2023年11月30日)限定公開され、ミライニ内のエンガワラウンジ(図書館カウンター側)にて12月13日~28日の期間に上映を行いました。

デラウェア賞(ゆかり)

最優秀賞(Alien)

優秀賞(SEVENTEEN・good day)

チャレンジ賞(酒田第一中学校)

リグル市長からのビデオ

参加者集合
酒田駅前交流拠点施設ミライニにて、『酒田の魅力紹介 in English 動画コンテスト』の受賞4作品を上映しました。来訪者の方々は「ここの喫茶店に行ってみたい」「飛島の景色はこんなにきれいなんだね」など、足を止めて映像をご覧になる方も多く、大盛況でした!

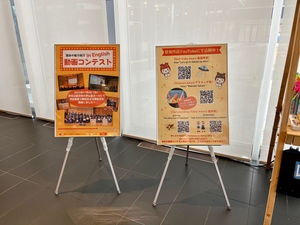
令和元年度SIRA事業「インターナショナル・おしゃべり・カフェ」、令和2年度「インターナショナル・おはなし・リレー」、令和3年度「インターナショナル・旅・リレー」に引き続き、本年度は「インターナショナル・座談会」を開催。オンラインにて、各回ごとに海外出身者などのゲストプレゼンターの皆さんが、メインテーマについてSDGsに触れながら自国・地元の文化や体験を紹介するトークショーです。
9月18日(日曜)に第1回『インターナショナル・座談会』を開催しました。
第1回目は「海外の食文化と食のサステナビリティ」をテーマに、酒田南高等学校グローバル専攻の生徒3名とフランス出身ピエールさん、フィリピン出身フェイリンさん、アメリカ出身キャサリンさんが地元の食文化やSDGsへの取り組み・事例について日本語と英語を使って紹介してくださいました。
はじめに、酒田南高等学校の生徒の皆さんが庄内の「TOCHITO」やフードドライブ、「tabeloop」という食品廃棄削減活動といった日本で行わているSDGsの取り組みについて紹介し、続いてピエールさんがフランスのお店や祭りで使用されるプラスチック容器の削減について、フェイリンさんは新しく取り組みが進んでいるパイナップルの生産プロジェクトについて、キャサリンさんはアメリカで伝統的なファーマーズマーケットが近年SDGsへの関心に伴い再び注目されていることについて、英語で紹介してくださいました。


SDGs画像出典:公益財団法人日本ユニセフ協会(![]() https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/about/(外部サイト))
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/about/(外部サイト))

食文化の紹介では、生徒の皆さんから山形の芋煮会のような食文化が海外にもあるのかという問いかけがあり、はじめにキャサリンさんが、感謝祭というアメリカの祝日で、毎年11月のこの日は家族全員でターキ―やキャセロールといった伝統料理を食べながら映画を見るなどの食文化について紹介してくださいました。

フェイリンさんは、フィリピンの食文化はフィリピンの歴史と深く結びつき、他国の影響を受けた料理が多いことを話してくださいました。例えば、フィリピンは7641の島々から成り立っている国だが、島ごとに他国の影響を受けた食文化があり、日本からはかき氷や豆腐を使った食文化が伝わっているそうです。

ピエールさんからは、出身地である南フランス・マントンのレモン祭りの様子やひよこ豆を使った伝統料理Socca(ソッカ)について話していただきました。レモン祭りではレモンを使ったオブジェクトが街中に飾られ、盛大なパレードが開催されます。また、ソッカはパーティーや特別な日に胡椒とオリーブオイルのシンプルな味付けで食べる伝統料理だそうです。
最後にプレゼンター同士の意見交換の場面では、地元の食文化を地元の人々だけでなく、海外など外に向けて発信していくべきではないか等の意見が飛び交うとともに、オンライン参加者からもプレゼンターに対する質問をいただくことで、各国のSDGsの取り組みや食文化について理解を深めることができたトークショーとなりました。
12月4日(日曜)に第2回『インターナショナル・座談会』を開催しました。
第2回目は「アドベンチャーツーリズムとSDGs」をテーマに、酒田南高等学校グローバル専攻の生徒3名とニュージーランド出身のティムさんが、英語でアドベンチャーツーリズムについて紹介してくださいました。
第1回目はZoomを使用したオンラインでの開催でしたが、今回はミライニ3階研修ルームチョウカイにて対面形式で開催し、22名の方にご参加いただきました。

はじめに、酒田南高等学校の生徒の皆さんが自分たちで考えた3つ(「水を巡る旅 in 酒田」「酒田の自然 大満喫プラン」「酒田でtry! 0円食堂」)の酒田でのアドベンチャーツーリズムプランとこれらのプランで取り組めるSDGsのポイントを発表してくださいました。
例えば、玉簾の滝の水でコーヒーを作り、傘福作りなどの北前船がもたらした文化体験、鳥海山からのパラグライダー体験や地元の人々との交流から食材を集め、オリジナルの酒田ラーメンを作るといった観光プランを提案していただきました。

続いてティムさんからは、出羽三山での山伏としての活動やニュージーランドのアドベンチャーツーリズム、SDGsの取り組みを紹介していただきました。
山形の人々の生活に影響を与えている山形の山々、修験道や山伏修行の基本「うけたもう」のお話から羽黒山の杉並木の保護活動、日本のペットボトル消費問題と比較したニュージーランドのマイボトル活動、ニュージーランド発祥のバンジージャンプといった人気のアウトドアアクティビティを紹介していただきました。中でもニュージーランドで開催されたゾンビランというゾンビに扮した鬼から逃げ回るイベントを飛島でやってみてはどうかという提案には会場から賛同の声が多く上がりました。
最後にプレゼンターと観覧者とのトークタイムでは、観覧者の方々からも英語で質問をいただき、対面形式ならではの時間を設けることができたトークショーとなりました。



1月21日(土曜)に第3回『インターナショナル・座談会』を開催しました。
第3回目は「ダイバーシティとSDGs」をテーマに、酒田南高等学校グローバル専攻の生徒3名とイギリス出身のエドさん、ニッキーさんと東北公益文科大学の学生が、日本語と英語を織り交ぜながら教育制度や学校生活について紹介してくださいました。
今回は前回に引き続きミライニ3階研修ルームチョウカイに加え、研修ルームミナトも使用して対面形式で開催しました。

はじめに酒田南高等学校グローバル専攻の皆さんから日本の一般的な教育制度とグローバル専攻の授業の比較、日本での大学進学について発表していただきました。
グローバル専攻の授業は、「新しい学びの形」としての時間割や1つのテーマを決めての発表など、イギリスの学校と似ている点があること、グループセッションを通して自分で考える力を高めること、ネイティブの先生との授業にて英語を話す機会が多く設けられていることなどが特徴的で、普段はなかなか知ることが難しいグローバル専攻の取り組みについて知ることができました。

続いて、イギリス出身のエドさんとニッキーさんからは、イギリスの教育制度やご自身が通った学校について紹介していただき、タツキさんよりイギリスの学校と日本の学校の違いについてお話していただきました。
イギリスの義務教育では、必修科目はなく自分が興味のある分野の教科を選び、時間割を自由に決められること、小学生の頃からコンピューターを使った授業があること、プリベイトカードを使って昼食を自分で買ってお金の使い方を学べることを紹介していただきました。
また大学の進学方法は、インターネットで1回申請するのみのシンプルな方法であることなど、日本との違いをたくさん教えていただきました。


2月18日(土曜)に『公益大生に聴く!ニュージーランドから学ぶ共生社会」を開催しました。
東北公益文科大学の武田真理子先生と武田先生のゼミに所属する学生3グループよりニュージーランドについて講演していただきました。

はじめに武田先生よりニュージーランドにおける多文化共生の歴史について英語でご講演いただきました。
ニュージーランドの国の成り立ちの歴史(先住民族マオリとヨーロッパ系パケハの歴史)、全国的最低賃金制度や女性の参政権導入など世界初の社会的施策・ジャシンダ・アーダーン元首相やニュージーランドにおける社会保障制度と社会福祉についてご紹介いただきました。
続いて、学生3グループによる研究成果発表を行いました。
1. 高齢者支援チーム「エイジズムの解消」
ニュージーランド在住者にインタビューを行い、日本とニュージーランドの高齢者施設の比較やエイジズムの解消方法について考察する。
2. 児童虐待といじめ問題の克服チーム「子どもを取り巻く問題について」
ニュージーランドのStand Christchurchの職員へのインタビューから日本とニュージーランドの児童虐待やいじめの現状や取り組みについて調査。
3. LGBTQとパートナーシップと結婚チーム「LGBTQから考える共生社会」
ニュージーランド滞在歴のある方にインタビュー調査を行い、日本とニュージーランドにおけるLGBTQへの理解度やパートナーシップ制度のギャップ等を調査。



3月19日(日曜)に『北庄内地域通訳案内士スキルアップ研修』を開催しました。
北庄内地域通訳案内士認定者を含む21名にご参加いただき、4月のクルーズ船寄港やコロナ収束後のインバウンド観光に備えた通訳案内研修を行いました。
はじめにVIPS(Volunteer Interpreting Partnaers of Sakata)代表の長南ジュディ氏より、クルーズ船寄港時やインバウンド観光時の通訳ガイドを通しての体験談、通訳ガイドに必要なことをご講演いただきました。
まち歩きの実地研修では、クルーズ船乗客へのガイドを想定した中町周辺の観光名所(山王くらぶ、相馬樓、日和山公園、小幡楼)を巡り、大人数を引き連れたガイド時の注意事項や観光地の説明の仕方などガイドのスキルアップを図りました。
研修当日はあいにくの天候により、当初のツアー行程を変更する場面もありましたが、相馬樓では施設内に入館し、舞娘の演舞鑑賞や施設内の見学をどのように行うべきか、外国人観光客に対して日本文化や酒田の歴史をどのように説明すべきか等を学びました。

3月29日(水曜)に高校生と大学生を対象とした『おもてなし英会話研修』を開催しました。
酒田に寄港する外国クルーズ船のお客さまへおもてなしを行うため、市内の高校生・大学生48名が参加しました。
講師に東北公益文科大学助教のティム・バンティング氏とALT6名をお迎えし、英語でのコミュニケーションの仕方をロールプレイングや中町での実地研修を通して教えていただきました。
第一部では酒田市よりクルーズ船の概要について説明があった後、東北公益文科大学助教のティム・バンティング氏より英語のコミュニケーションについてご講演をいただきました。
また、ALTと参加者によるグループワークでは、ALTが観光客役となり、参加者に酒田でおすすめの観光施設や飲食店について聞くなどロールプレイングを行いました。


第二部では、4月14日(木曜)寄港のダイヤモンド・プリンセスのお客さまのために、高校生による「ドキドキおもてなしツアー」の実地研修を行いました。
文化体験コースでは、当日同様に会場設営を行い、体験の練習をしました。ALTの方々より観光客役になっていただき、体験に使う英語のフレーズや単語を学びました。
まちあるきコースでは、日和山公園・海向寺・山王くらぶを訪問し、まちあるきガイド時の注意事項や英語での効果的な会話を学びました。
参加者にとっては初めての外国人観光客へのおもてなしとなるため、積極的にメモを取ったり質問をしたりとクルーズ船寄港に向けて英語力の向上に取り組んでいました。



市民部 共生社会課 男女共同参画・多文化共生係
〒998-0044 酒田市中町三丁目4番5号 交流ひろば内
電話:0234-26-5615 ファックス:0234-26-5617